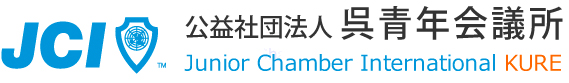理事長 平岡 達也
【基 本 方 針】
驚きの連鎖で変化を起こす
【スローガン】
BIGBANGs
【所 信】
1. はじめに
私の人生は「環境」に恵まれていたと思う。
小学生の頃、Jリーグ開幕の流行に乗ってサッカーを始めたが、練習の厳しさにすぐに挫折してしまった。そんなとき、友人がソフトボールに誘ってくれた。 最初はまったく打てなかったが、毎日素振りを重ねるうちに少しずつ上達し、卒業する頃には試合でも活躍できるようになった。そして、その後も高校まで野球を続けることになった。
大学時代、私は決して成績が優秀だったわけでも、司法試験に合格する確たる見通しがあったわけでもなかった。
それでも「自立したい」「就職活動をして組織に属するのは嫌だ」という思いから、就活をせずにロースクールに進学した。1日中机に向かう生活を3年間続け、最終的に司法試験に合格することができた。
当時の私は、それらの成果をすべて「自分の努力の結果」だと思っていた。
けれど、あらためて振り返ってみると、その努力を始めるきっかけを与えてくれたのも、それを支え、続けさせてくれたのも、周囲の「環境」の力だったことに気づかされる。
もし友人が誘ってくれなければ、素振りに付き合ってくれる指導者がいなければ、勉強を教えてくれる先生がいなければ・・・自分はどうなっていたのだろう。
今では、自分に素晴らしい環境を与えてくれた人たちに対して、心からの「驚き」をもっている。
子どもたちが成長していく「環境」は、放っておいて自然にできあがるものではない。
だからこそ、私たちは、このまちの子どもたちが将来振り返ったときに驚きを与えるような環境をつくっていかなければならない。
「驚き」があふれるまちへ。
その変化の起点となる「BIGBANG」を呉のまちに生み出していく。
2.「やればできる」を育む挑戦の場づくり
私が小学生の頃に入ったソフトボールチームは、子ども向けとは思えないほど厳しいチームだった。
中でも、夏休みに行われる合宿は、私にとって恐怖と言っても過言ではなく、「行きたくない」「最後まで耐えられるだろうか」と不安ばかりが募り、バスに揺られて球場に向かう道中は、憂鬱そのものだった。
それでも、真夏の厳しい練習に仲間と声を掛け合いながらなんとか耐え抜き、最後までやりきり、自宅への帰途に着いたとき、不思議と「自分が成長した」ことを実感した。
それは、自分の不安を乗り越えたことにより得られた達成感であった。
こういった幼少期の成功経験がなければ、私は、その後の人生において、司法試験や、事務所の独立といった様々な挑戦をすることもなかった。
もちろん、挑戦することが常に正解であるとは限らない。
しかし、変化が激しい現代社会では、「正解」を誰もが見いだし難くなっている。人材育成においても、これまでの「正解のある問題に正しく答える力」を育てる教育だけでは通用しない。
むしろ、コミュニケーション力や柔軟性、共感力、粘り強さといった、失敗を糧として再び挑戦する力こそが重要である。
こういった力は、問題に直面し、試行錯誤を重ねながら、他者と関係性を築いていく中で、ひとつひとつ課題を乗り越え、「やればできる」という成功体験を積み重ねることで育まれていく。
しかし、定量的な評価が難しく、学校教育の現場では評価やカリキュラムへの導入が難しいとされており、十分な教育実践が行われていない現状がある。
だからこそ、私たち呉青年会議所が、子どもたちが「やればできる」と感じられるような、挑戦の場を創り出していく。
困難に挑み、仲間と支え合い、そして乗り越える――
これにより、子どもたちが、未知の世界と出会い、新しい仲間と出会い、そして今まで知らなかった自分と出会い、驚きを実感する。
このような経験をした人材が、これからの変化が著しい社会で活躍し、呉のまちを支えていく。
3.歴史と文化の記憶を未来へつなぐ
私は広島市で育ったが、呉市で生活していた祖母から「原爆が落とされたとき、呉からも光るのが見えた」と聞いたことがある。
しかし、それ以上の話を祖母から聞くことはないまま、昨年、祖母は94歳でこの世を去った。
今にして思えば、呉で起こった戦時中の出来事や、戦後の暮らしの様子、地域に息づく文化について、もっと話を聞いておけばよかったと悔やまれるが、もう二度と聞くことはできない。
いま私たちは、かつてないほどの不確実性の中に生きている。
テクノロジーの急激な進展や地政学的な緊張、価値観の多様化などにより、これまでの常識や前提が次々と揺らぎ、「自分はどこに属しているのか」「何のために生きているのか」といった根源的な問いが、多くの人にとって切実なものになっている。
こうした時代において、人が「自分が何者か」を見失わずに生きていくためには、帰る場所となる精神的な拠り所が重要となる。
それは、単なる地理的な故郷ではなく、「その土地の歴史や文化」「人々の営み」「語り継がれる記憶」といったものの蓄積によって培われる地域アイデンティティという土壌である。
まちに息づく歴史や文化を未来に継ぐことは、ただ過去を保存するためではない。
それは、次の世代が自分のまちに誇りを持って社会を生き抜くための「精神的インフラ」を築く行為である。
しかし今、その継承は確実に難しくなってきている。
後継者不足、資料の消失、証言の風化―― 一度失われれば、二度と取り戻すことはできない。
私はこれまで、旅行のたびに戦争に関する記念館をよく訪れてきた。
沖縄県平和祈念資料館、知覧特攻平和会館、国立広島原爆死没者追悼平和記念館――どれも膨大な記録が保存されており、その圧倒的な量と密度に、言葉を失う。
あれほどの記録を残し続けているのは、「忘れない」という強い意思があるからだ。
私たちもまた、呉のまちに関する歴史文化を、未来に残す意思をもって継承していかなければならない。
4.驚きの連鎖を生み出す組織へ
「そこまでやるか」の実践
初めて呉青年会議所の例会に参加したとき、私はその厳粛で緊張感のあるセレモニーに、大きな驚きを覚えた。単に形だけ姿勢を正したり、声を出したりしているのではない先輩方の覚悟を感じたからである。
私たち呉青年会議所は、市民の皆さまに「そこまでやるか」という驚きを与える組織である。
そうであるならば、会員の意識統一の場である毎月行われる例会、とりわけセレモニーを、厳粛で緊張感のあるものとすることで、驚きを与える組織であるという会員の意識統一を図ることが重要である。
とはいえ、セレモニーを形だけ厳粛で緊張感のあるものとするのではなく、その意味や理由について会員一人一人の理解を促し、腹落ちした上で実践することが重要である。
「そこまでやるか」の実践を通じて、青年会議所の運動の意義や事業構築の方法に関する学びを各自が得ることができる機会を提供する。
繋がる広報
私は2020年に広報委員長をさせていただいたが、1つ後悔していることがある。
それは、自分が適時に情報を発信することのみにとらわれてしまい、「伝わる」のではなく、「伝える」広報活動に終始してしまったことである。
今や2020年よりも更に時代は進んでおり、情報を「伝わる」かたちで届けることはもちろんのこと、市民の方々と「繋がる」ことが重要となっている。
「繋がる」ことを通じて、何が「伝わる」情報であるのかといった分析もより確度の高いものとなる。
また、呉青年会議所の貴重な財産として「JCで一皮むけた経験」というコンテンツがある。これはホームページでも公開されているが、呉青年会議所の諸先輩方がこれまでどのようなことをしてきたのか、そして、どのようなことをきっかけに成長を実感したのかということがまとめられている。私もJC活動をする上で、迷ったときなどは適宜参照してきた。
このようないわば「対内広報」ともいうべき広報活動を行い、呉青年会議所が何をしてきたのか、呉青年会議所でどのようなことを学べるのかといったことに関する会員や特別会員、関係者の「物語」を残し、繋げることで、驚きの連鎖を生み出す組織としての意識統一をはかる。
徹底的にサポートする拡大
正直に申し上げると、私は、青年会議所が何をする団体なのか、どのような人がいる団体なのか、どれくらい時間を使うのかといったことを何も知らずに入会した。
そのため、とりあえず入会したのはいいものの、仮入会員となってからも、しばらくの間活動から足が遠のいていた。
しかし、そんな時でも、アカデミー委員会の委員の方は、メークアップで他LOMの例会に連れて行ってくださったり、食事に連れて行って話を聞いてくださったりして、徹底的にサポートしてくださった。そのおかげで、私は今でも青年会議所活動をしている。
仮入会員の期間というのは、青年会議所活動の一部しか知ることができない。
無防備だった私とは違い、多くの方は慎重である。
だからこそ、将来の仲間と出会い、私たちの活動への共感を生み、実際に仲間に加わってもらうためには、徹底的に仮入会員期間をサポートし、その不安を解消し、期待に応え得る組織であることを伝え続ける必要がある。
そのための情報収集、資料作成、コミュニケーションの在り方などといった一つ一つのプロセスを整理工夫し、会員全員で徹底して実施していく。
5.おわりに
「青年会議所とは何をする団体だろうか?」
青年会議所の信条である「JCI Creed」は、「人類への奉仕が人生最大の使命である」という一文で締めくくられている。
私たちは、仕事で収入を、家庭で愛情を得ることに多くの時間を使う。
それだけでも忙しいのに、なぜ「奉仕」が必要なのか。
この問いに対する私なりの一つの答えを得たのが、2020年のことだった。
この年、私は広報委員長として、前年度中から事業計画の立案や準備、ホームページや会員手帳の作成などに取り組んでいた。
ところが、2020年1月に国内で初めて新型コロナウイルス感染症の患者が確認されると、2月には全国的に自粛ムードが広がり、4月には緊急事態宣言が発出された。
「ステイホーム」が推奨され、人が集うことは当たり前ではなくなった。
多くの会合や事業が中止され、当時の私は「活動を止めるべきではないか」と考えていた。
しかし、呉青年会議所は、「コロナ禍でも、できることを工夫してやりきる」という理事長の方針のもと、例会や事業の開催方法を模索しながら、可能な限り活動を続けていった。
もし皆が「仕事」と「家庭」のことしか考えなかったとしたら、地域の経済活動や教育、歴史文化の継承といった営みは徐々に停滞していく。そしてその影響は、やがて自分たちの「仕事」や「家庭」にも跳ね返ってくる。
そして、このことは、コロナ禍のような危機的状況だけでなく、冒頭で話したように、人の成長にとって環境が極めて重要であることともつながっている。
誰かが、私たちの幸せの土台を作ることに取り組まなければならない。
青年会議所は、行政でも、営利企業でも、家庭でもない。経営者団体でもない。
独自の立場から、「まち」のことを考え、行動する団体である。
自分の成長が誰かの支えによってなし得たものであることに気付き、今度は自分が誰かの成長を支える番としての責任を果たす覚悟を持つ。
これはまちづくりでも、青年会議所活動でも同じだ。
2026年度、呉青年会議所は、まちの未来を見据え、「環境をつくる側」としての自覚をもって活動を展開していく。
第74代理事長 平岡 達也